からだの味
村松真理
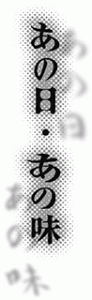
ただのクリスチャンです。
と言うと、すこしへんな響きがするかもしれない。そこにどんな気持ちをこめているかというと、〈といって、教義について詳しく知っていて正確な説明ができるわけではなく、聖書のすみずみまで頭に入っているわけでもなく、いまや毎週欠かさず教会に通っているわけでもなく、つねに信仰にもとづいた行動をとれているとはとてもいえません、うーん情けない、それでも、やっぱり私はそうです〉ということになる。
ミッションスクールに通っていたことはないので、とくに宗教団体による大きな事件が起きた十代のころは、お弁当を食べる前のお祈りはなんとなくこそこそとやり、仲の良い友達以外には言わなかった。大学に入ると、言えばしばしば現代人の信仰とは何なのかという類の議論をふっかけられるのに閉口した。その人達が聞きたいのは私の実感ではなくて、手応えのある反論や解説なので、だいたいがっかりされる。おまえ、それでも神を信じてるって言えるの。
そうなんです。と思ったから、自分で決めた。日本のプロテスタントの教会の多くはそうだ。子供の頃から教会に通っていても、自分で決められる年齢になってから決める。決めないまま通い続ける人もいる。大人になってから教会に来る人、高齢になってから洗礼をうける人もたくさんいる。見てわかるわけじゃない。見てわかるのは、聖餐式のときだけだ。
「最後の晩餐」の絵に描かれた、イエスが十字架につけられる前夜の、弟子たちとの食事を記憶する儀式。私が通っている教会では月一回、順番に聖餐卓のまえに出て行き、牧師先生から銀色のお皿の上の、小さなさいころ型に切りわけたパンと、ショットグラス(こんな喩(たと)えしか浮かばないところがじつに情けない)よりもっと小さいガラスのグラスに分けたぶどう汁をいただく。全員が終わるまで、まだ洗礼を受けていない人はただ待っている。長椅子に座ったまま、膝を縮めて前に出て行く人たちを通し、戻ってきた人たちをまた通す。「あれって、ちょっと疎外感だよね」と、十代の頃誰かが言って、あ、きみもそう思ってたの、となんだかほっとしたことを覚えている。
「これはあなたがたのために裂かれたキリストのからだです」「これはあなたがたのために流されたキリストの血です」と、牧師先生が繰り返すことばが、その頃はどぎつく思えて、少し怖かった。突然怖く思わなくなったときに、その列に加わった。
食べるということは、どぎついくらい真剣なことだ。私が食べたもののからだで、私のからだができている。
〈ただのクリスチャン〉なのに、食べもの、食べること……とぼうっと考えていたら、こんなことを思いだしてもうほかへ移れなくなった。ふまじめだと思われたら、どうか、ご容赦願いたい。
はじめて口に入れた、小さな「キリストのからだ」は、普通のパンの味がした。教会員のひとりが焼いて持ってくる。ぱさぱさしていて、飲みこみにくい。続いてぶどう汁がまわってくるので、どのタイミングで飲みこむか、などと、同年代の子達と冗談半分に話したことがある。ぶどう汁はシロップのように甘い。教会で一年分まとめてつくる。
学生のころ半年ほどドイツにいたことがあり、プロテスタントの聖餐といってもさまざまなのを知った。カトリックで使うような丸い味のないウエハースだったり、甘くないほんもののワインだったり、それを大きな杯で回し飲みだったりもした。
聖餐をうけるようになってから、東京で就職するまでの短い間、「聖餐用具管理」というお役をもらっていた。管理といってもお片付け係である。手袋をして器を下げ、専用のクリームで磨き、グラスはふつうの洗剤で洗う。グラスに分けてしまった「血」のほうは仕方ないけれど、銀の皿に残った細切れの「からだ」はまとめてビニール袋に入れる。「残りはいつも〇〇さんに渡すことになってるの」と、同じ係の先輩がいった。庭にくる鳥にあげるのだそうだ。 (『望星』2015年2月号掲載)
むらまつ・まり●1979年生まれ。2005年「雨にぬれても」で第12回三田文学新人賞を受賞。15年、村松茉莉名義でSFファンタジー小説『夢想機械 トラウムキステ』を刊行。

