納豆を希求する我が意識
須藤岳史
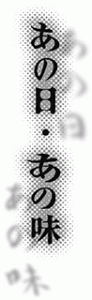
もう長いこと海外で暮らしている。多文化主義を採るオランダは多くの移民を受け入れてきた歴史があり、様々な国籍が入り乱れている。もちろん多くの社会問題も浮上してきているが、現在のところ約二十パーセントが外国人というメトロポリタンな国家だ。
こんな環境のため、様々な国籍の人と出会う機会も多い。そんな折に、しばしば「オランダでは何を食べていの? やはり和食中心?」という質問を受ける。僕はパンが嫌いなので、ほとんど食べない。ほぼ毎朝ご飯を鍋で炊く。夕食は様々。妻の祖国であるポーランドの家庭料理の日もあれば、和食、イタリア料理、フランス料理、オランダ料理、スペイン料理、インド料理、中華料理、タイ料理、トルコ料理などなんでも無頓着に食べる。こんな回答をすると「和食をあまり食べられなくてかわいそうね」という反応をされるが、そういえば日本でも多くの人がこのような多国籍食文化を普通に営んでいることを思い出す。
戦時中に書かれた坂口安吾の『日本文化私観』は興味深い一冊だ。日本文化の本質を躊躇なく描写しており、この主張を理解できなければ日本文化を語る資格はない、と僕は思う。安吾は伝統文化を徹底的に斬る。そして、伝統や国民性と呼ばれるものに隠された欺瞞を暴く。「伝統の美だの日本本来の姿などというものよりも、より便利な生活が必要」「古いもの、退屈なものは、亡びるか、生れ変るのが当然だ」等々、一見傲慢ともとれる発言が続く。この理由は、最終章「美に就て」で明らかになる。ここは是非皆さんにも実際に読んで頂きたいので詳細を省くが、安吾の興味は「実質を伴う美しさ」にあり、「美しさのための美しさは素直でない」「空虚なものは、その真実のものによって人を打つことは決してなく、詮ずるところ、有っても無くても構わない代物である」と主張する。美しさは目的ではなく、美しさだけでは何者でもないということだ。
ここで思い出すのは柳宗悦。宗悦は西洋化に伴って失われゆく日本の伝統文化を目の前にし、生活に即した実用的な民芸品にこそ美があるという「用の美」を唱えた。アプローチは異なるが、安吾と同様、美しさが実用的なものに宿る点を強調していることは大変興味深い。
伝統的な日本文化が忘れ去られていると嘆く人は多い。しかし、考えてみれば、真の日本文化とは日本人の精神性そのものであり、日々何かを生み出し、消し去り、また創るという営みのダイナミズムにあるのではないか? これは自然災害の多い風土とも深く関係しているだろうし、泡沫無限な世の鏡像とも言える。文化はモノではなく、それを生み出す人間自体にある。安吾は「日本古代文化を見失っているかも知れぬが、日本を見失う筈はない。日本精神とは何ぞや、そういうことを我々自身が論じる必要はないのである」と言う。日本人が着物より洋服を好み、西洋風の食事をしても日本文化はびくともしない。新たな習慣が伝統となるのに必要なのは、歴史や時間といった付加的な物語だけだ。
歴史的な芸術作品に初めて触れた場合、その魅力を理解できないという体験は誰にでもあると思う。遠い昔の作品に宿る「美しさ」の発見は、成立背景や歴史を含む様々な物語に支えられて初めて達成される場合が多い。日本の伝統文化は、僕たちの生活から乖離してしまっており、予備知識なしでは心に響かないという場合もあるだろう。こういった場合に考えるべきことは、「付加的な物語を取り去った後に、いったい何が残るのだろうか」ということだ。そして、文化を生み出す主体である我々自身を深く見つめ直す必要があることは言うまでもない。
閑話休題。肝心の食についてまだ何も書いていなかった。オランダに来て始めたのは納豆作り。日本食材屋でも冷凍の納豆を買えるが高い。そこで自分で作ってみることにした。一晩水につけた大豆を柔らかくなるまで煮る。食材屋で買った貴重な納豆を四分の一パックほど混ぜて密封し、セントラルヒーティングの上に。あとは一日に数回軽く混ぜるだけで数日後には懐かしの納豆が出来上がる。自家製の納豆は冷凍モノより百倍くらいおいしい。納豆のタレはないので鰹節を豪快に載せ、醬油をかけ、アツアツの白いご飯の上に。オランダの乾いた空気と納豆の芳香が混ざり「僕はいったいどこにいるのだろう?」という不思議な気分になる。オランダで作る納豆は日本という文脈から離れているかもしれないが、それでいいのだ。出来立てで、まだ温かい納豆を食べながら「納豆を希求する我が意識の志向性こそ日本文化の真髄」などと思案する初夏の夕べである。 (『望星』2013年10月号掲載)
すどう・たけし●1977年茨城県生まれ。ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者。ブルージュ国際音楽コンクールでディプロマ賞受賞。ディオニソス・コンソート音楽監督。オランダ・ハーグ市在住。

