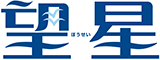選評:水島久光(第2回)
他者の味覚の謎を解く
 「食」の行為の記憶は、日常のものでありながら、時にとんでもない非日常をひきつれてやって来る。その豊かさ、複雑さを、これでもかというくらい味わって、お腹いっぱいになった選考会だった。それは何よりもまず、身近にいた人への思いとともにある。特に家族は一筋縄ではいかない。言葉の壁が立ちはだかる。近いからこそ変によそよそしい、暖かいようで時に重いその存在はいくつになっても割り切れず「腹に落ちない」。
「食」の行為の記憶は、日常のものでありながら、時にとんでもない非日常をひきつれてやって来る。その豊かさ、複雑さを、これでもかというくらい味わって、お腹いっぱいになった選考会だった。それは何よりもまず、身近にいた人への思いとともにある。特に家族は一筋縄ではいかない。言葉の壁が立ちはだかる。近いからこそ変によそよそしい、暖かいようで時に重いその存在はいくつになっても割り切れず「腹に落ちない」。
最優秀賞の「クルミ味のストロガノフ」は、それがドラマのワンシーンのように迫まってくる作品だった。「暴君」「うそぶく」「言い出したら聞かない」……そうした描写とともにあった父親が発する「クルミ味がする」という一言。どんな味なんだろう。他人の味覚こそ究極の謎である。それを思い出すことから、作者は父親への心の距離を縮めようと考え始める。
佳作の「ばばの焼きそば、B級グルメ」は、作者と亡くなった母親との距離を、息子の記憶の中にある焼きそばが縮めていく物語である。味だけではない。絵が次々浮かんでくる。「ばばはね、ホオズキをブーブーって鳴らしながら焼きそばをつくるんだ」。疎ましかった母をなぜ息子は愛おしく思い出すのか。謎は解けない。でも次第に「頰がゆるんでくる」。
優秀賞の「三等兵と水餃子」も謎に満ちている。作ってくれたのは焼き餃子。でもその父が中国で食べていたのは水餃子のはず。なぜ水餃子をつくらないのか。そしてそれはどんな味なのか。わからないことだらけである。それはおそらく、戦後生まれの作者の、戦争に対する思いなのかもしれない。
食の記憶は、失われた時代や地域の風景につつまれている。それが生きていくことの厳しさの中での、空腹を満たす行為であったとしても、我々の郷愁は強く喚起される。しかしその地域特有の食材となると、味は全く想像の彼方だ。「なんこ」「きなこめし」……これはいったい何なのだろう。謎だ。でもなんだか、香りがしてくるようだ。
文章を読んでいるだけで、五感が立ち上がってくる。食のエッセイの面白さだ。「ブサイクなソフトクリーム」には笑った。さりげなく書かれた「母になる覚悟」が胸を打った。食を語ることで、人は優しくなれる。
●みずしま・ひさみつ
1961年生まれ。メディア社会学者。東海大学文化社会学部広報メディア学科教授。著書に『メディア分光器