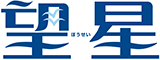夢中でうなずいた母の言葉
 「あの日あの味」という言葉が、大好きです。最初からひとつの言葉のように、優しくつながって胸に響いてきます。
「あの日あの味」という言葉が、大好きです。最初からひとつの言葉のように、優しくつながって胸に響いてきます。
「あの日」があったからこそ、「あの味」が忘れられないという当り前のことに、はたと教えられた気がします。確かにそうだったのだわ、と、この言葉からなつかしい思い出がよみがえってくるのでした。
昭和29年の初夏、幼い私は母と二人、山手線の恵比寿駅のガード下から程近い雨もりのするバラックの二階の一間に引っ越しをしてきました。上京して、まもない頃のことでした。母の仕事はおいそれとみつからず、朝晩ごはんにお醤油をかけて食べるだけの毎日が続きました。ついにお米を買うお金もなくなったある日の夕暮れ、母とガード下の市場のあたりをとぼとぼ歩いていました。ふと、市場のゴミ箱の横に、じゃが芋がひとつ転がっているのに気が付いたのです。
「ゴミ箱の傍に落ちているのだから、これをいただいても泥棒にはならないわね」 母の言葉に、夢中でうなずきました。
その晩、母娘二人で食べた茹でたてのじゃが芋は、夢のようにおいしく思われました。今でもあつあつのじゃが芋を口にするたびに、あの日のことを思い出します。私のもっとも大切な思い出です。
心の中に生き続けるかけがえのない思い出を、「あの日あの味」のエッセイを通して教えていただけたら、どんなに幸せでしょう。
太田治子(選考委員長)
作家。父は太宰治、母は太田静子。明治学院大学文学部卒。86年『心映えの記』で坪田譲治文学賞受賞。著書に『母の万年筆』『明るい方へ』『時こそ今は』『夢さめみれば 日本近代洋画の父・浅井忠』『石の花 林芙美子の真実』『星はらはらと 二葉亭四迷の明治』など。