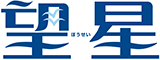広州の学生食堂
倉数 茂
 「食は広州に在り」と言う。正確には「生在蘇州、衣在杭州、食在広州、死在柳州」と言って、風光明媚な蘇州に生まれ、杭州の有名な着物を着て、広州の料理を食べ、柳州産の高級棺桶におさまるのが最高だ、という意味らしい。棺桶の良し悪しなんてものにこだわる意味があるのか不明だが、その広州(グワンヂョウ)に二年ほどいた。今から八年ほど前の話である。
「食は広州に在り」と言う。正確には「生在蘇州、衣在杭州、食在広州、死在柳州」と言って、風光明媚な蘇州に生まれ、杭州の有名な着物を着て、広州の料理を食べ、柳州産の高級棺桶におさまるのが最高だ、という意味らしい。棺桶の良し悪しなんてものにこだわる意味があるのか不明だが、その広州(グワンヂョウ)に二年ほどいた。今から八年ほど前の話である。
当時、わたしは文学研究を専門とする大学院生で、そもそもそんな誰の役に立つのだかまったくわからないものを生業(なりわい)としているのだから収入などろくになく、将来の見通しがまったくたたないうえに、文部省(当時)が一九九〇年代にぶちあげた院生倍増計画がようよう成果をあげだして、就職のあてのないドクター、ポスドクは雲霞のごとく、高学歴ワーキングプアなどということばもちらほら巷間で耳にするようになった頃だった。
ところがそんなとき、何を血迷ったか結婚してしまう。となれば、活計(たつき)の道を考えねばならぬ。おりよく中国で日本語教師の口を紹介してくれる人があって、大陸は広州に飛んだ。
思えば、若かった。いや、実年齢で言えば、すでにおっさんになりかけだったのだが、今後のキャリアはどうなるのかとか、月給七万(現地採用だったのでそれくらい)でどうするのかとか、何も考えていなかった。ただ、いつまでつづくぬかるみぞ、終りの見えない院生暮らしに別れを告げ、新天地で新婚生活を始めるというだけで胸が高鳴った。
結果から言えば、いい選択だったと思う。初めての海外生活というだけで刺激的だが、中国社会はこちらの予想を超えて、ダイナミックであり、多様であり、混沌としていた。ちょうど日中関係が急速に悪化していく時期にあたっていたのだが、マスコミの報道だけでは得られない皮膚感覚での中国を感じることができた。明るい面も暗い面も見たけれど、底知れぬ魅力を持った国であることだけはまちがいない。
さて、その刺激に満ちた中国生活の中でも、楽しみなのが食べることだった。
食在広州は本当なのだ。これは広州料理の味わいを讃えることばだと思われているが、本当は、広州の料理屋をほめているのではないかと思う。華南きっての大都市広州には、職を求めて省外から出稼ぎが流入し、自然、四川料理、重慶料理など中国各地の料理屋が店を並べている。これらがこれまたうまいのだ。広州料理は当然美味だが、他の料理の店でもがっかりした記憶がない。
広州は古い商都であって、広州人の気性はドライで闊達(かったつ)、そのうえ食道楽が多くて、安くてもうまい店でなければたちまち潰れてしまうのだろう。料理人にすれば気の抜けない街である。日本で言えば大阪に似ている。
宴会などでたまに招待される高級レストランは当たり前のことながらおいしかった。味わいは上品で繊細、見た目は華麗で調理法も多彩。
けれどもなんともうれしかったのが、学生がたむろっているような安い飯屋のうまさである。高級レストランの上品さとは違う、もっとストレートでがつんと来る味。日本で食べる中華料理と何が違うのかと思うのだが、日本人の舌になじませようとするとどうしても素材の味を重視して、味噌や醤油の旨みを利かせるという味の組み立てになるのではないだろうか。一方、中華料理はショウガ、にんにく、油をおしみなく使い、さらに八角だの唐辛子だのといった香辛料が豪勢に自己主張する。大陸の中国料理を食べなれると、日本の中華はおしなべてマイルドでおとなしいような気がする(それはそれで好きですが)。
もっとも湖南料理など体力気力が充実していないと食べられない。舌を鈍器でたてつづけに殴られているのじゃないかと思うくらいの辛さだ。あまりの辛さに声が出なくなり、涙や鼻水が溢れ出しているのに箸が止められないという不思議。
では広州を再訪するとしたら、どこへ行きたいか。実は、勤め先の大学の学生食堂だ。いまどき日本の大学ではまず見られないような殺風景な食堂である。発泡スチロールの容器にご飯をつめてもらい、カウンターに並んでいるおかずを指差すと、調理のおばちゃんがおたまですくって飯の上にぶっかけてくれる。おかずのつゆが交じり合おうが、容器から溢れ出そうが関係なし。容器を持っているこちらの手もべとべと。おかず三種類で四元(五十円強)くらいだった。
もう一度あのぶっかけ飯を食べてみたい。だけど今の中国の変化の速度を考えると、あの学生食堂も今頃は案外小奇麗なカフェテリアに変っているのかもしれない。 (『望星』2014年4月号掲載)
くらかず・しげる●1969年生まれ。作家。東海大学文学部文芸創作学科講師。著書に『魔術師たちの秋』『黒揚羽の夏』(以上小説)、『私自身であろうとする衝動』(評論)、『北の想像力』(共著)ほか。